【報告】朽木中学3年生「朽木の未来を考える授業」2日目
2019年03月13日
卒業前の朽木中学3年生と朽木の未来を考える授業をさせていただきました。
朽木中学は、卒業後ほとんどの生徒が地域外へ通学し、地域に関る機会が減ってしまいます。中学生が故郷の未来を考える授業の中で、故郷に残したい価値や地域資源に気づく機会にしてほしいと思いました。また、中学生が考えた故郷の未来について、朽木地域のみなさんに伝えたいと考えました。
1月24日は「朽木で無くなってほしくないこと、無くなると残念だと思うこと」について哲学対話をしました。
報告はこちらをご覧ください。(リンクする)
1月31日は、哲学対話で話された内容を整理しながら、30年後の朽木にあってほしい暮らしやものやことについてグループでまとめていきました。

まとめ方は、○○を残す(目的の)ために、○○がある(といい:手段)を考えて整理していきました。
例えば、
●自分以外の人も自分のことのように目を向けて手をかけられるような人の暖かさ。
を残すために・・・
・地域ごとにある小さな祭り(があるといい)
(理由)集落のなかでご飯を食べるとかは、大切。
例えば、
●朽木の木、自然
を残すために・・・
・小中学校での自然とかかわる時間の授業(があるといい)
(具体的には)どんぐりの苗を植えた授業が心に残っている。
30年後の朽木にどのようなことを残したいのか(目的)、そのための手段はなにか。という視点でまとめていきました。まとめながら、さらに必要な手段を付け加えていきました。
各グループで整理した図にタイトルを付けて発表しました。

画像をクリックすると大きくなります。
「朽木の未来」
●近所や地域の方のかかわり方を残したい
●自分以外の人も自分のことのように目を向けて手をかけられるような人の暖かさ
を残すために・・・
・野菜のおすそわけがうれしい(つけもの、しし肉)
・家に近所の人がいる→安心 いろんな話しができる
・お手伝いする(雪どけ、草刈、畑、たんぼなど)
・「寄り合い処くっつき」を残す
「野菜のおすそ分けをする」「近所の人が家を訪ねる」「近所でお手伝いする」ことがあるとよい。
●地域ごとにある小さな祭り
●鯖・美・庵祭りとかいろいろな祭り(桜祭り、スポーツカーニバル、文化祭)
理由:自分の存在を感じられる スポーツカーニバルとか集落のメンバーとして
を残すために・・・
・若い人が受け継ぐ
・祭りの時に帰ってくる
・友達のいる地域の祭りに行く
●小中学校で自然とかかわる時間の授業
理由:どんぐり苗を植えた授業が心に残っている。
人生で経験できないことができる(木を植える)
普段、見られない景色を見られる(チャレンジトレイル)
●丸八百貨店
理由:小さい頃からおばあちゃんとよく行っている。
昔は学校帰りに寄っていた(おやつを買ったり)
を残すために・・・
・生徒数を維持する
・朽木の良さを発信する
・2階をBARにする
・図書館、生協にする

画像をクリックすると大きくなります。
「朽木を良くするために」
●良い環境のアピール
●朽木の自然との関わりを深くする
を残すために・・・
・朽木のよさを取り入れた校舎にする。(朽木の木を使う)
●企業を増やす、林業に関わる
●若者を増やす
を残すために・・・
・企業とコラボ
・地区の事業を増やす
●便利にする
ために・・・
・自動販売機を各地区に設ける
・バスの本数を増やす
●会話を増やす
ために・・・
・地区内にある小さな祭り
・地区の事業を増やす

画像をクリックすると大きくなります。
「いつまでも人が暮らせる環境」
●保育園、小学校、中学校が残っている。
そのために・・・
・自由な暮らしができる(大声出しても怒られない、畑や田んぼができる)
・お店はなんでも配達可能なお店
・保育園は、遅くまで子どもを見てくれる
●住んでいる集落が残っている。
そのために・・・
・鯖・美・庵祭りとかいろいろな祭り
・近所/地域の方との関わり
・介護の仕事
●朽木の木・自然が残っている。
そのために・・・
・森の面倒を見る仕事(林業、観光)
・小中学校での自然とかかわる時間の授業
●人とのふれあい
を残すために・・・
・コーラス、歌のある地域
・みんなで集まってご飯を食べる時間をつくる
・地域ごとにある小さな祭り(人が来てくれるような祭り)
・丸八百貨店
●自分以外の人も自分のことのように目を向けて手をかけられるような人の暖かさ
を残すために・・・
・お互いに必要なものをあげたり、もらったりする関係をつくる
発表を聞きながら、中学3年生が朽木地域で暮してきた中で、何を大切だと感じているのかが見えてきた気がしました。地域の方々に聞いていただきたいと思いました。
この授業は4時間で終了しましたが、今日、故郷の将来について考えたこと、自分たちが残してほしいと思った大切なものやことについて話したことが、みなさんの心に残っていくことを願っています。
(報告:坂下)
朽木中学は、卒業後ほとんどの生徒が地域外へ通学し、地域に関る機会が減ってしまいます。中学生が故郷の未来を考える授業の中で、故郷に残したい価値や地域資源に気づく機会にしてほしいと思いました。また、中学生が考えた故郷の未来について、朽木地域のみなさんに伝えたいと考えました。
1月24日は「朽木で無くなってほしくないこと、無くなると残念だと思うこと」について哲学対話をしました。
報告はこちらをご覧ください。(リンクする)
1月31日は、哲学対話で話された内容を整理しながら、30年後の朽木にあってほしい暮らしやものやことについてグループでまとめていきました。
まとめ方は、○○を残す(目的の)ために、○○がある(といい:手段)を考えて整理していきました。
例えば、
●自分以外の人も自分のことのように目を向けて手をかけられるような人の暖かさ。
を残すために・・・
・地域ごとにある小さな祭り(があるといい)
(理由)集落のなかでご飯を食べるとかは、大切。
例えば、
●朽木の木、自然
を残すために・・・
・小中学校での自然とかかわる時間の授業(があるといい)
(具体的には)どんぐりの苗を植えた授業が心に残っている。
30年後の朽木にどのようなことを残したいのか(目的)、そのための手段はなにか。という視点でまとめていきました。まとめながら、さらに必要な手段を付け加えていきました。
各グループで整理した図にタイトルを付けて発表しました。

画像をクリックすると大きくなります。
「朽木の未来」
●近所や地域の方のかかわり方を残したい
●自分以外の人も自分のことのように目を向けて手をかけられるような人の暖かさ
を残すために・・・
・野菜のおすそわけがうれしい(つけもの、しし肉)
・家に近所の人がいる→安心 いろんな話しができる
・お手伝いする(雪どけ、草刈、畑、たんぼなど)
・「寄り合い処くっつき」を残す
「野菜のおすそ分けをする」「近所の人が家を訪ねる」「近所でお手伝いする」ことがあるとよい。
●地域ごとにある小さな祭り
●鯖・美・庵祭りとかいろいろな祭り(桜祭り、スポーツカーニバル、文化祭)
理由:自分の存在を感じられる スポーツカーニバルとか集落のメンバーとして
を残すために・・・
・若い人が受け継ぐ
・祭りの時に帰ってくる
・友達のいる地域の祭りに行く
●小中学校で自然とかかわる時間の授業
理由:どんぐり苗を植えた授業が心に残っている。
人生で経験できないことができる(木を植える)
普段、見られない景色を見られる(チャレンジトレイル)
●丸八百貨店
理由:小さい頃からおばあちゃんとよく行っている。
昔は学校帰りに寄っていた(おやつを買ったり)
を残すために・・・
・生徒数を維持する
・朽木の良さを発信する
・2階をBARにする
・図書館、生協にする

画像をクリックすると大きくなります。
「朽木を良くするために」
●良い環境のアピール
●朽木の自然との関わりを深くする
を残すために・・・
・朽木のよさを取り入れた校舎にする。(朽木の木を使う)
●企業を増やす、林業に関わる
●若者を増やす
を残すために・・・
・企業とコラボ
・地区の事業を増やす
●便利にする
ために・・・
・自動販売機を各地区に設ける
・バスの本数を増やす
●会話を増やす
ために・・・
・地区内にある小さな祭り
・地区の事業を増やす

画像をクリックすると大きくなります。
「いつまでも人が暮らせる環境」
●保育園、小学校、中学校が残っている。
そのために・・・
・自由な暮らしができる(大声出しても怒られない、畑や田んぼができる)
・お店はなんでも配達可能なお店
・保育園は、遅くまで子どもを見てくれる
●住んでいる集落が残っている。
そのために・・・
・鯖・美・庵祭りとかいろいろな祭り
・近所/地域の方との関わり
・介護の仕事
●朽木の木・自然が残っている。
そのために・・・
・森の面倒を見る仕事(林業、観光)
・小中学校での自然とかかわる時間の授業
●人とのふれあい
を残すために・・・
・コーラス、歌のある地域
・みんなで集まってご飯を食べる時間をつくる
・地域ごとにある小さな祭り(人が来てくれるような祭り)
・丸八百貨店
●自分以外の人も自分のことのように目を向けて手をかけられるような人の暖かさ
を残すために・・・
・お互いに必要なものをあげたり、もらったりする関係をつくる
発表を聞きながら、中学3年生が朽木地域で暮してきた中で、何を大切だと感じているのかが見えてきた気がしました。地域の方々に聞いていただきたいと思いました。
この授業は4時間で終了しましたが、今日、故郷の将来について考えたこと、自分たちが残してほしいと思った大切なものやことについて話したことが、みなさんの心に残っていくことを願っています。
(報告:坂下)
タグ :朽木のみんなと円卓会議
Posted by たかしま市民協働交流センター at
16:14
│たかしま・未来・円卓会議報告
【報告】朽木中学3年生「朽木の未来を考える授業」1日目
2019年03月13日
たかしま市民協働交流センターでは、平成27年から朽木のみんなと円卓会議に取り組んできました。
過疎高齢化が進む朽木地域で、世代や立場を越えて、若者も高齢の方も男性も女性も一緒に地域の課題や価値について話をし、一人ひとりができることに気づき、ともに取り組むきっかけとなる機会を作りたいと、朽木住民福祉協議会とともに地域の人々の対話の場づくりをしてきました。
これまでの取組は、朽木のみんなと円卓会議をご覧ください。(別ウインドウで開きます)
※朽木のみんなと円卓会議は、琵琶湖環境科学研究センターの方、総合地球環境学研究所の方他のご協力で進めています。
今年は、卒業前の朽木中学3年生と朽木の未来を考える授業をさせていただきました。
朽木中学は、卒業後ほとんどの生徒が地域外へ通学し、地域に関る機会が減ってしまいます。中学生が故郷の未来を考える授業の中で、故郷に残したい価値や地域資源に気づく機会にしてほしいと思いました。また、中学生が考えた故郷の未来について、朽木地域のみなさんに伝えたいと考えました。

授業のスケジュール
1月24日(木)5時間目、6時間目
哲学対話
・朽木で無くなってほしくないこと、無くなると残念だと思うこと
・朽木の方に聞いてみる「30年後、こんな朽木であってほしい」
朽木住民福祉協議会の方、森林公園くつきの森の方、地域の子育てママの集まり
「きりかぶの会」の方に来ていただき、一緒に対話しました。
1月31日(木)3時間目、4時間目
グループワーク
・30年後の朽木にこんな暮らしがあるといい
・グループ発表
授業のスケジュールと朽木の人口推計、一年前の朽木の未来へつなぐ物語づくりについて説明しました。
哲学対話
哲学対話は、対話をとおして、分からないことや問題に気づくこと、一緒に考えること、自分の言葉で語ること、そしてお互いに耳を傾けることを大切にしていきます。
安心して対話をするためのルールです。
☆朽木地域での哲学対話の取り組みはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開きます)
5時間目の哲学対話で話されたこと
朽木でなくなったら残念だと思うこと、なくなって欲しくないこと
■保育園、小学校、中学校
(理由)自分が育ったから。
■住んでいる集落
■朽木の木、自然
(理由)好きだから。
(心配事)人が減ると、森も面倒みる人がいなくなって困るなあ。
■丸八百貨店
(理由)小さいころからおばあちゃんとよく行っている。
■地域ごとにある小さな祭り
(理由)集落のなかでご飯を食べるとかは、大切。
■鯖・美・庵祭りとかいろいろな祭り(桜祭り、スポーツカーニバル、文化祭)
(理由1)ボランティアしていて楽しい、好きだ。普段会わない人と会う機会。
(理由2)お店とか手伝うことでお店の人とも仲良くなれる。働く体験。
■コーラス、歌のある地域
■小中学校での自然とかかわる時間の授業
(具体的には)どんぐりの苗を植えた授業が心に残っている。
■近所/地域の方とのかかわり
(理由)高齢者の人とかかわるときは新しい知識がもらえることがあるので。
■自分以外の人も自分のことのように目を向けて手をかけられるような人の暖かさ
対話の中では、学校で教えてほしいことについても出てきてました。
■社会に出たときに役立つようなこと。社会に出たときに恥ずかしくないような常識を教えて欲しい。マナーとか知らないと怒られることだってあると思う。
■人が亡くなっときに、どんなふうにお葬式出したらいいのか、といったこと。
6時間目は、地域の方から30年後の朽木地域についてお話を聞き、哲学対話を続けました。
朽木住民福祉協議会の方のお話
誰かが困っている時、道を歩いている時、お互いに声をかけられる地域であってほしい。おせっかいかもしれないけれど、何か困っているようだ、暮らしにくそうだと思われる人がいたら、声をかけあえる気持ちのこもった人間関係のある地域であってほしいと思う。
森林公園くつきの森の方のお話
自然は人が関ると優しくなります。宮本常一さんは「自然はさびしい。しかし人の手が加わると暖かくなる」と言われた。集落も森林も人がかかわり、心地よい風景であればいい。
子育てママの集まり「きりかぶの会」の方お話
今は朽木の誰もが顔を知っている人のつながりを大切だと感じるし、ずっと残していきたい。朽木中学に通っていた頃ははとても窮屈に感じていた。ママになって、「自分」になれる時間の大切さを感じた。訪問看護の仕事を始めて、人のつながり、自然のよさを感じることができるようになった。
1.朽木にずっと住んでいたい?それとも、朽木を出たい?
◆ずっと住んでいたい
・みんな、ほとんどの人が知っている人。他の所に行ったときにそういう関係が一回切れてしまうとちょっと後が怖いし、まだこの関係を続けたい。
◆出たい
・一回出て、新しい知識とかを入れたい。
・何をするのにも、遠くへ行かないといけないし、それにお金もかかってくるので、もっと、コンビニとかが近くにあるところ。都会に住みたい。
・朽木の山奥の集落が好きだけれど、山奥すぎる。もうちょっと気楽にいろんな所に行ける方がいいかな。でも、朽木くらいの人数が好き。
・高校とか考えるときに、ここに住んでいるから、どこの高校にするにも距離を考えないといけない場面が多かった。子どもができた時とかは、そういう事情であきらめたくない。とはいえ、それなりに自然のある都市部に近いところに住みたいなと思う。
◆一度出たいけど、いつか戻ってきたい
・今の自分が、何ができるかというのを試したい。
・いろんな所(都会、日本各地、海外)に行って、いろんな経験をしたりしたい。それでもやっぱり朽木は大切。
・一回朽木じゃない所に出て、あー朽木ってやっぱりいいとこやなって思ったら、もう一回帰って来たいなって思う。
・人生で一度は、都会とか行って、すぐにお買い物とか、近所のお店で買い物する暮らしをしてみたい、けどそれは一度経験したいだけ。
・朽木の人間関係はめちゃめちゃいいと思うが、朽木じゃないところにも実際行って住んで、新しい人間関係を作っていきたい。また朽木に戻ってきたときに、今までと同じ近い人間関係だったら一番いい。
・(物騒なので)朽木から出たら殺されてしまうかも、と思ってしまう。
2.将来帰ってきて、朽木で暮らしていくためにどんな仕事をしていたい?
・高齢者が多い。だから、介護の仕事とか。そのために都会に行って、資格を取って、またここに戻ってきて、普通に実家暮らしがしたい。
3.朽木のどんないいところが見えてきた?
・情報が回るのが速い。誰かが亡くなったとか。逆にいいことも回ったりすると思う。
それぞれに将来のことを考えて、対話した時間となりました。
1月31日は、対話したことを整理して、30年後の朽木にあるといい暮らしや風景について考えました。
こちらをご覧ください(別ウインドウで開きます)
(報告:坂下)
過疎高齢化が進む朽木地域で、世代や立場を越えて、若者も高齢の方も男性も女性も一緒に地域の課題や価値について話をし、一人ひとりができることに気づき、ともに取り組むきっかけとなる機会を作りたいと、朽木住民福祉協議会とともに地域の人々の対話の場づくりをしてきました。
これまでの取組は、朽木のみんなと円卓会議をご覧ください。(別ウインドウで開きます)
※朽木のみんなと円卓会議は、琵琶湖環境科学研究センターの方、総合地球環境学研究所の方他のご協力で進めています。
今年は、卒業前の朽木中学3年生と朽木の未来を考える授業をさせていただきました。
朽木中学は、卒業後ほとんどの生徒が地域外へ通学し、地域に関る機会が減ってしまいます。中学生が故郷の未来を考える授業の中で、故郷に残したい価値や地域資源に気づく機会にしてほしいと思いました。また、中学生が考えた故郷の未来について、朽木地域のみなさんに伝えたいと考えました。

授業のスケジュール
1月24日(木)5時間目、6時間目
哲学対話
・朽木で無くなってほしくないこと、無くなると残念だと思うこと
・朽木の方に聞いてみる「30年後、こんな朽木であってほしい」
朽木住民福祉協議会の方、森林公園くつきの森の方、地域の子育てママの集まり
「きりかぶの会」の方に来ていただき、一緒に対話しました。
1月31日(木)3時間目、4時間目
グループワーク
・30年後の朽木にこんな暮らしがあるといい
・グループ発表
授業のスケジュールと朽木の人口推計、一年前の朽木の未来へつなぐ物語づくりについて説明しました。
哲学対話
哲学対話は、対話をとおして、分からないことや問題に気づくこと、一緒に考えること、自分の言葉で語ること、そしてお互いに耳を傾けることを大切にしていきます。
安心して対話をするためのルールです。
☆朽木地域での哲学対話の取り組みはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開きます)
5時間目の哲学対話で話されたこと
朽木でなくなったら残念だと思うこと、なくなって欲しくないこと
■保育園、小学校、中学校
(理由)自分が育ったから。
■住んでいる集落
■朽木の木、自然
(理由)好きだから。
(心配事)人が減ると、森も面倒みる人がいなくなって困るなあ。
■丸八百貨店
(理由)小さいころからおばあちゃんとよく行っている。
■地域ごとにある小さな祭り
(理由)集落のなかでご飯を食べるとかは、大切。
■鯖・美・庵祭りとかいろいろな祭り(桜祭り、スポーツカーニバル、文化祭)
(理由1)ボランティアしていて楽しい、好きだ。普段会わない人と会う機会。
(理由2)お店とか手伝うことでお店の人とも仲良くなれる。働く体験。
■コーラス、歌のある地域
■小中学校での自然とかかわる時間の授業
(具体的には)どんぐりの苗を植えた授業が心に残っている。
■近所/地域の方とのかかわり
(理由)高齢者の人とかかわるときは新しい知識がもらえることがあるので。
■自分以外の人も自分のことのように目を向けて手をかけられるような人の暖かさ
対話の中では、学校で教えてほしいことについても出てきてました。
■社会に出たときに役立つようなこと。社会に出たときに恥ずかしくないような常識を教えて欲しい。マナーとか知らないと怒られることだってあると思う。
■人が亡くなっときに、どんなふうにお葬式出したらいいのか、といったこと。
6時間目は、地域の方から30年後の朽木地域についてお話を聞き、哲学対話を続けました。
朽木住民福祉協議会の方のお話
誰かが困っている時、道を歩いている時、お互いに声をかけられる地域であってほしい。おせっかいかもしれないけれど、何か困っているようだ、暮らしにくそうだと思われる人がいたら、声をかけあえる気持ちのこもった人間関係のある地域であってほしいと思う。
森林公園くつきの森の方のお話
自然は人が関ると優しくなります。宮本常一さんは「自然はさびしい。しかし人の手が加わると暖かくなる」と言われた。集落も森林も人がかかわり、心地よい風景であればいい。
子育てママの集まり「きりかぶの会」の方お話
今は朽木の誰もが顔を知っている人のつながりを大切だと感じるし、ずっと残していきたい。朽木中学に通っていた頃ははとても窮屈に感じていた。ママになって、「自分」になれる時間の大切さを感じた。訪問看護の仕事を始めて、人のつながり、自然のよさを感じることができるようになった。
1.朽木にずっと住んでいたい?それとも、朽木を出たい?
◆ずっと住んでいたい
・みんな、ほとんどの人が知っている人。他の所に行ったときにそういう関係が一回切れてしまうとちょっと後が怖いし、まだこの関係を続けたい。
◆出たい
・一回出て、新しい知識とかを入れたい。
・何をするのにも、遠くへ行かないといけないし、それにお金もかかってくるので、もっと、コンビニとかが近くにあるところ。都会に住みたい。
・朽木の山奥の集落が好きだけれど、山奥すぎる。もうちょっと気楽にいろんな所に行ける方がいいかな。でも、朽木くらいの人数が好き。
・高校とか考えるときに、ここに住んでいるから、どこの高校にするにも距離を考えないといけない場面が多かった。子どもができた時とかは、そういう事情であきらめたくない。とはいえ、それなりに自然のある都市部に近いところに住みたいなと思う。
◆一度出たいけど、いつか戻ってきたい
・今の自分が、何ができるかというのを試したい。
・いろんな所(都会、日本各地、海外)に行って、いろんな経験をしたりしたい。それでもやっぱり朽木は大切。
・一回朽木じゃない所に出て、あー朽木ってやっぱりいいとこやなって思ったら、もう一回帰って来たいなって思う。
・人生で一度は、都会とか行って、すぐにお買い物とか、近所のお店で買い物する暮らしをしてみたい、けどそれは一度経験したいだけ。
・朽木の人間関係はめちゃめちゃいいと思うが、朽木じゃないところにも実際行って住んで、新しい人間関係を作っていきたい。また朽木に戻ってきたときに、今までと同じ近い人間関係だったら一番いい。
・(物騒なので)朽木から出たら殺されてしまうかも、と思ってしまう。
2.将来帰ってきて、朽木で暮らしていくためにどんな仕事をしていたい?
・高齢者が多い。だから、介護の仕事とか。そのために都会に行って、資格を取って、またここに戻ってきて、普通に実家暮らしがしたい。
3.朽木のどんないいところが見えてきた?
・情報が回るのが速い。誰かが亡くなったとか。逆にいいことも回ったりすると思う。
それぞれに将来のことを考えて、対話した時間となりました。
1月31日は、対話したことを整理して、30年後の朽木にあるといい暮らしや風景について考えました。
こちらをご覧ください(別ウインドウで開きます)
(報告:坂下)
タグ :朽木のみんなと円卓会議
Posted by たかしま市民協働交流センター at
15:47
│たかしま・未来・円卓会議報告
朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その3:朽木の未来に残したいことや今からできることを対話する)
2018年06月07日
朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その3)
2017年の「朽木のみんなと円卓会議」は、朽木地域のありたい未来を地域の人々が話し合い、その未来に向かって今からできることを考える機会を作っていきました。
6月には、未来への地域ストーリーづくり勉強会を開催し、地域の人々が地域の未来について想像し、そこにつながるストーリーを話し合う体験をしていただきました。
報告はこちらをご覧ください(別ウインドウで開きます)
8月から9月、朽木の未来へつなぐ物語づくりを始める前に、朽木で活動する市民グループの方々にお会いして、「朽木らしさ」や「朽木の将来のイメージ」などを聞き取りました。朽木の人々の思いを未来へのつなぐ物語づくりの素材にしました。
報告はこちらをご覧ください(別ウインドウで開きます)
これまでの朽木のみんなと円卓会議報告もご覧ください(別ウインドウで開きます)
11月から2018年2月、4回に分けて朽木の未来へつなぐ物語づくりを開催しました。
開催案内はこちらをご覧ください(別ウインドウで開きます)
1回目の11月26日(日)、2回目の12月10日(日)、どちらも13:30~16:00、朽木保健センターで開催しました。
内容は、朽木地域意識調査の結果と朽木地域で活動する市民グループから聞き取った内容を聞いていただきました。そして、参加された方が想像する30年後の朽木に残したいものやことについて話ていただきました。
残念ながら、イベントが重なったりで、参加してくださったのは、最初の2回でのべ3名。
でも、じっくりとお話することができました。

参加されたのは、お二人とも移住された方。朽木で子育て中のお母さんでした。
朽木らしさや地域に残していきたいものやことについて、いろいろと挙げてくれました。
これまでの聞き取りと、この2日間でお話してくれた内容をまとめました。
30年後の朽木に残したいもの、こと、暮らし
●何かあったらみんなで駆けつける消防団や地域の人々のつながりを残したい
●ハレの日や法事などで作っていた、朽木の伝統の家庭料理を残したい」
●おばあが働けて、誰でも立ち寄れて、誰かに会えて、子どもも預けられる丸八百貨店を残したい
●人とつながっている安心感、イザという時に声かけあえる人のつながりを残したい
●盆踊り、地域で人が顔を合わせ、一緒にできる行事を残したい
●里山や森林に人の目が向いて、人が関り、人が入れる里山を残したい
30年後の朽木にあるといい仕組み
●朽木で暮したいという移住者を温かく迎え入れ、集落での暮しに入ってもらえる仕組みがある
●地域の人と子どもを結ぶ学校を残したい。少人数でゆったり過ごせる学校を選択できる仕組み
●田畑を使いたい人、里山や森林の維持に関る仕事をしたい人、土地に関りたい人が住める仕組み
●伝統の行事を受け継げるカタチに変えてつないでいく仕組み
●独りになっても安心して暮せる仕組み。一緒に暮せるシェアハウスの仕組み
3回目の2018年1月21日(日)、4回目の2月4日(日)も13:30~16:00に、朽木保健センターで開催しました。
この2回は、参加者はのべ12名。年齢は30歳代から60歳代の方々でした。
3回目は、上記の「30年後の朽木に残したいもの、こと、暮らし」「30年後の朽木にあるといい仕組み」を見ていただき、さらに書き加えたいことを出していただきました。また「目的」と「手段」を整理しながら、30年後にあるといい朽木のことを話していただきました。
4回目は、30年後の朽木に残したいものや仕組みについて、「目的」と「手段」を整理した図を見ていただき、さらに書き加えることなどを話し合ったあと、30年後の朽木に向けて「今からできること」「5年後の朽木」「10年後の朽木」「20年後の朽木」について話していただきました。
お母さんと一緒に子ども達も来てくれて、とても賑やかになりました。
「子どもをこんなぎょうさん(たくさん)見たのは久しぶりや~」という声が出てました。
書き加えたこと
●みんながお互いに分かっている安心感が30年後にもあるといい
●山に係われて仕事になるといい。山の木が手入れできて、間伐して、木材を使いたい人がいて、お金が回る仕組みがほしい
●山の境界をはっきりさせる。若い世代が山で働ける
●広葉樹を植えて、しいたけのホダ木にしたり、炭の原料にして仕事につながるといい
●古民家や茅葺屋根の家を移住者や使いたい人が使えるといい。移住者が増えないと先細り
●退職してUターンする人が増えるといい
●山の境界線などを次の世代が引き継げる仕組みが必要
●山の資源の使い方、山菜の知識、炭焼きの技術など山を使うための技術を残す
●朝市の場、誰かに喜んでもらえる場が必要
●朽木でしか学べないことを学べる学校があるといい
●朽木の学校林はどうなってる?保護者もみんな関りたい
「目的」と「手段」の整理を下記のようにしました。
目的1:人とつながっている安心感、イザという時に声かけあえる人のつながりを残したい
目的1のための手段
○何かあったら駆けつける消防団がある
○ハレの日の伝統の家庭料理を伝える(伝統の家庭料理教室、祭りの機会などで)
○伝統の行事や料理を受け継げる形に変えて受け継ぐ
○おばあが働けて、誰でも立ち寄れて、子どもも預けられる丸八百貨店がある
○盆踊りや地域で人が顔を合わせて一緒にできる行事(運動会なども)がある
○朽木で暮したい移住者を温かく迎え、集落での暮しに入ってもらえる仕組みがある
○独りになっても安心して暮せる仕組み、シェアハウスのような仕組みがある
目的2:人が関り、人が入れる里山を残したい
目的2のための手段
○山の資源の使い方、山菜の知識、炭焼きの技術など山を使うための技術がある
○田畑を使いたい人、里山や森林の維持に関る仕事をしたい人、土地に関りたい人が住める仕組みがある
○朽木で暮したい移住者を温かく迎え、集落での暮しに入ってもらえる仕組みがある
○古民家や茅葺屋根の家を移住者や使いたい人が使える
○広葉樹を植えて、しいたけのホダ木にしたり、炭の原料にして仕事につながる
○山の境界をはっきりさせる。若い世代が山で働ける
目的3:朽木らしい特色ある学校を残したい
目的3のための手段
○地域の人と子どもを結ぶ学校がある
○少人数でゆったり過ごせる学校を選択できる仕組みがある
○学校林に子どもも保護者も関わる
目的4:移住者を増やす
○朽木で暮したい移住者を温かく迎え、集落での暮しに入ってもらえる仕組みがある
○田畑を使いたい人、里山や森林の維持に関る仕事をしたい人、土地に関りたい人が住める仕組みがある
○古民家や茅葺屋根の家を移住者や使いたい人が使える
○少人数でゆったり過ごせる学校を選択できる仕組みがある
参加者のお話から30年後のありたい朽木の未来として「広葉樹の森が朽木の人と暮らしと伝統をつなぐ」を中心に、目的と手段を図にして、さらに必要なことを出していただき、書き加えていきました。
盛り上がったお話
特色ある学校では、朽木でしか学べないことが学べるといい。例えば、山菜のこと、炭焼き、川の生きもの、朽木の暮らしの知恵を持っている地元のおじいや伝統の家庭料理を教える地元のおばあが講師になって学校で教えてくれるといい。「サバイバル力のある子が育つ」という学校になってほしい。こんな学校に入りたいという子どもが学校を選べるといい。そんな学校を目指して、家族で移住する人が来るといい。
広葉樹がたくさんあれば、炭焼きをし、原木しいたけを育てられる。昔はそんな暮らしが朽木にあった。約15年で広葉樹は再生する。広葉樹の森を資源に暮らしていける。山の木の伐り方、炭焼きの仕方、山菜のことなど今から学んでおかないと、教えられる人がいなくなる。こんな魅力的な朽木の暮らしや風景を発信する人がいるといい。明るく、新緑も紅葉も美しい広葉樹の森は観光資源にもなる。朽木のさまざまな魅力を観光資源としてコーディネートして発信したり、提供できる人がいるといい。それも仕事になる。その前に、朽木のみんなが朽木の魅力を知ってるようになるといいのに。
道路の端の針葉樹は台風や雪で倒れて迷惑。針葉樹の暗い森には子どもも大人も入りにくい。広葉樹の森なら、いろんな人が入ることが出来て、獣害も減るだろう。どうやったら、誰が決めれば、この針葉樹を切れるのだろう? 昔は、もっと川の水が多かった。広葉樹の森になれば水量も増えて、魚も増えるだろう。
朽木の暮らしやすさは、人がみんな知っていること。丸八百貨店のような、おばあも子どもも安心して寄れる場があるといい。寄り合い処くっつきのような場もあるといい。独りになっても安心して暮らせるといい。年とるとわがままにもなるし、一緒に暮すシェアハウスは難しいかな。昼間は一緒に過ごせて、食事は一緒にできるといい。最期まで人の世話にならないと生きてはいけない。いや、死んでからも最期は人の世話になる。それなら、気安い人の近くに住めるといい。最期まで自分の家にいたいと言ってるおばあの声を聞いている。地域のみんなで見守って、家で最期を迎えられることが選択できるようになるといい。
人が増えないと先細る。空き家や田畑を移住者や使いたい人に貸せるようにできるといい。特色のある学校があったり、山に関る仕事ができたり、朽木の魅力が発信されて、移住したいという人が来て、地域にも受け入れる雰囲気があるといい。何より、今日のような朽木のこれからを話してることも発信していけるといい。
今からできること、5年後、10年後、20年後の朽木の姿について、思い浮かぶところから話していただきました。

<今からできること>
●朽木のこと、地域のこと、誰でも気軽に話せる場所(お酒も飲みながら)を作る
●朽木に残しておきたいこと(料理や技術や伝統のこと)などを知っている人のリストを作る
 誰が、何を知っていて、どうやって残すのかを考えるために
誰が、何を知っていて、どうやって残すのかを考えるために●学校林に植える苗づくりや植樹をもっと頻度を増やす。保護者も一緒にできることで何か関りたい
●炭焼きを学ぶ + 炭焼きの原料の確保の方法も学ぶ
●睦美会のメンバーを募集する
●丸八百貨店をもっと使って、いろんな人に来てもらう
●今ある「朽木のいいこと」を発信して、若い人を呼び込む + 朽木の人が「朽木のいいこと」に気づく
<5年後>
●炭焼きを自分たちでできている + 炭焼きの原料を確保する技術を持っている
●朽木の魅力発信コーディネーターが仕事をしている
●コーディネートする事務所がある
●龍治さんや地域の知恵や技術を持っている人が、月1回は学校で講師をしている
<10年後>
●丸八百貨店を若手(40代くらい)も一緒に運営している
●あたりまえに地域の中で助けあっている
●林業家、フォレスターが増える
●育林の技術を持つ人が増える
●杉の木の価値が上がっている
<20年後>
●道路沿いは全て広葉樹になっている
●朽木が森林の再生と活用のモデルになっている
●朽木の人工林、杉林の半分くらいは広葉樹になっている
●鳥も魚も水も増えている
●朽木と森に魅力を感じて、移住者が増える
みなさんのお話をまとめた30年後の未来の朽木地域の図です。
(画像をクリックすると大きくなります)

みなさんが話された30年後の朽木地域に向けて、できることです。
(画像をクリックすると大きくなります)

4回の中では、本当にいろいろなお話をお聞きすることができました。
物語というカタチにまではなりませんでしたが、世代や年代を越えて、一緒に朽木のこれからを話すという目的には近づけたかと思います。みなさんが話された30年後の朽木地域に向けて、今からできることが、一つでも二つでも実現されるように、お手伝いができればと思います。そんな朽木の人々の歩みが物語になっていくといいなと思っています。
報告:たかしま市民協働交流センター 坂下
お問合せ
たかしま市民協働交流センター
高島市今津町中沼1-4-1 今津東コミュニティセンター内
TEL 0740-20-5758
FAX 0740-20-5757
E-mail webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp
HP http://tkkc.takashima-shiga.jp/
Posted by たかしま市民協働交流センター at
09:38
│たかしま・未来・円卓会議報告
朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その2:朽木の市民グループへへ聞き取り)
2018年06月07日
朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その2)
2017年の「朽木のみんなと円卓会議」は、朽木地域のありたい未来を地域の人々が話し合い、その未来に向かって今からできることを考える機会を作っていきました。
6月には、未来への地域ストーリーづくり勉強会を開催し、地域の人々が地域の未来について想像し、そこにつながるストーリーを話し合う体験をしていただきました。
報告はこちらをご覧ください(別ウインドウで開きます)
これまでの朽木のみんなと円卓会議もご覧ください(別ウインドウで開きます)
8月から9月、朽木の未来へつなぐ物語づくりを始めるために、朽木で活動する市民グループの方々にお会いして、「朽木らしさ」や「朽木の将来のイメージ」などを聞き取りました。
お会いした朽木の市民グループ(リンクは別ウインドウで開きます)
・NPO法人麻生里山センター 5名
・朽木住民福祉協議会 3名
・雲洞谷栃餅保存会 1名
・きりかぶの会 4名
・睦美会 9名
・生活支援ボランティアグループでんでん虫 14名
・たかしま おさんぽ会 3名
・上針畑防災福祉組 5名
・千年桜の会 3名
・くつきうーまんず 2名
・朽木花火師会 2名


「朽木らしさ」
みなさんから聞き取った「朽木らしさ」です。
・言葉。古い言葉残ってたなあ。おばあちゃんが使っていた。いま使うのかなあ。「きょうとい」って、気疎い(けうとい)かな。
・お地蔵さんがいっぱいある。
・お寺、法事、先祖をすごく大事にしている。
・人はまるい。すれてない。警戒はしはる。
・地域の盆踊り★世代を越えて「盆踊り」が挙げられました。
・朽木さんへの信頼感が絶対ある。
・朽木内結婚が多かった。葛川や久多からも。
・水路。暮らしの中に水の流れがある。
・普請がすごく多い。水路の掃除。草刈。基準が厳しい。だからきれい。
・若いときは朽木村と住所を書くのが嫌だった。今は誇れる。異文化の所、独特と思われる。
・みんな知っている。誰でも、どこでも、顔を知っている。どこで何しててもバレバレ。知らない人に話しかけられる。
・運動会の司会をしている人が「どこどこの○○さん、どこそこの○○さん」と全て言える。
★多くの人が「知っている人が多い中での暮し」を話してくれました。
・80代の方は、若い頃、絶対1回は京都・大阪に出ている。わりと都会的。
・みなさん「女性がおしゃれ」と言う。おばあちゃんたちも身づくろいをきちんとしている。着るものにしていも、なんでもいいというわけではなくて、自分に似合う服を着ている。
・見えないところで、つながりあっている、知っている、助けてもらえる。イザとなれば、あの人に言えば何とかなるというのがあると、安心感がある。
・これやったら作れるよ。家にあるよ。同世代の若い人でもチェーンソー使える。がんばればできんことがない。困ったことがあっても助け合える。
・近所の諸先輩方に伺うのが、ここなりの(暮らしの)術。
・診療所の先生は子どもの同級生のお父さん。役場の人はPTAのメンバーでもある。一人で何役も顔がある。郵便局、消防団、同じ区の人など。
「朽木の将来のイメージ」
みなさんから聞き取った「朽木の将来のイメージ」です。
・今よりも年寄りばかりのイメージ。移住者みたいな方が来やすくなるといいな。ばあさん連中、愛想ようするし。
・(小学校などが少人数であることについて)現在はいいけど、ここから先細っていったときに(どうなるか)・・・
・もっと子どもが複数の保育園・小学校(どこかと朽木)を出たり入ったりしてもよいのでは。もっと気軽に選べたらいい。
・一人になる(独居で暮す)期間が長いから、大きいところに共同で住みたい。部屋は別で。みんなと一緒に共同生活。で一人にもなれる(スペースもある)。亡くなってもすぐに見つけてもらえる。
・将来的にここ(の集落)に居続けたいけど、無理なときが来る。まとまって生活できる。そういうとこを作っとかないとあかんな。
・行事をとおして子どもをつないでいく。祭りがなくなった集落は、人が帰ってこーへん。
・大人が楽しんでる姿を子どもが見てて、大人になって楽しんでくれれば。
★何人もの方が同様のことを話してくれました。
・小さな団体でもアピールする。一緒にしーひん?ということがつながっていったら、ほんまのネットワークになる。
・年はいってても「(ささえあい)できるよ」という人との連携。
・60歳過ぎて、仕事を減らせてちょっと余裕ができて、地域のことに目を向けることができるようになった人が、ある程度の期間、地域のことで活躍できる人生のプランを根づかせたい。
・(集落の)幕引きが一番の問題。片付け方もある、一つの地域のあり方。
・地域がなくなることが本当に悲しいことなのかを見つめないと。郷土愛、ご先祖様を意識しながら考える。
・(針畑への観光は)中型バスでちょこちょこ来るのが一番いい。
※聞き取りのまとめは、地球研の熊澤さんがされました。
聞き取りの内容と2017年3月の朽木地域意識調査の結果を、11月の朽木文化祭で発表しました。
朽木地域意識調査結果をご覧ください(別ウインドウで開きます)
11月から2018年2月に、参加者を募り朽木の未来へつなぐ物語づくりを開催しました。
朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その3)へ続きます(別ウインドウで開きます)
Posted by たかしま市民協働交流センター at
09:35
│たかしま・未来・円卓会議報告
朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その1:未来への物語づくり勉強会)
2018年06月04日
朽木の未来へつなぐ物語づくり 報告(その1)
たかしま市民協働交流センターは、朽木住民福祉協議会のみなさんと一緒に、朽木住民福祉活動計画を具体化するための取り組みとして、2015年度より「朽木のみんなと円卓会議」を実施してきました。
2015年は「朽木でずっと伝えていきたいものってなんだろう」をテーマに、朽木の伝統保存食「へしこ」を使って、さまざまな年代の方が一緒に、へしこの漬け方、へしこの食べ方、へしこを使った新しいメニューづくりをして、朽木地域で伝えていきたいものやことについて対話をしました。
小さなお子さん連れのママ・パパから60代の方まで、のべ40名の参加者がへしこ料理を一緒に調理して、食べて、朽木地域のことを対話しました。
2016年は「朽木でずっと残していきたいものってなんだろう~世代をつなぐ朽木の今昔写真」をテーマに、市場地域と針畑地域で、地域の昔の写真を使って、みんなで朽木地域に残していきたいものやことについて対話しました。
昔の写真を見ながら暮らしや学校、産業などについて高齢の方からお話を聞き、昔の写真と今の風景を見比べて、何が変わったのか気づいたことを対話しました。時とともに変化してきた朽木地域を知った後、未来に残したいものやことについて、未来の朽木地域に暮す人へのメッセージとして参加者同士で発表しました。針畑地域では、移住を考えている若い夫婦へ地域の自慢を伝えるメッセージを考えました。
お子さん連れのママから80代の方まで、のべ70名の参加者が、朽木でずっと残したいものや祭りなどの行事、風景などについて対話しました。
また、朽木地域で中学生以上の住民を対象にした朽木地域意識調査も実施しました。

これまでの朽木のみんなの円卓会議の報告をご覧ください(別ウインドウで開きます)
2017年は、朽木の未来を語り合える場を作りたいと「朽木の未来へつなぐ物語づくり」をテーマに開催しました。
朽木地域の30年後のありたい風景や暮らし、産業などを想像し、お互いにどんなことやものを大切にしたいと思っているのか、そして今から何をすれば、ありたい未来につながるのかを対話する目的で実施しました。
朽木の未来への地域ストーリーづくり勉強会を開催しました。
6月17日(火)19:30~21:30
朽木公民館
参加者 11名
まずは、なぜ未来への地域ストーリーづくりを企画しているのかお話をしました。
地域の未来を想像して、どんな未来の暮らしや仕事や祭りなどがあるといいかな・・・と考え、地域の人々が対話をすることで、自分たちが大事にしたいこと、地域の価値などに気づく機会になります。また、今から未来へつながるストーリーを考えることで、今からできることについて考え、対話することができます。さまざまな人が一緒に、朽木の大事にしたいこと、今からできることを対話できる機会をつくりたいと思います。
今回のワークでは、参加者に3つのグループに分かれていただき、テーマを選んで話し合っていただきました。
テーマは、2016年度の「朽木でずっと残していきたいものってなんだろう」ワークや「朽木地域意識調査」の結果から提示させていただきました。
※「朽木でずっと残していきたいものってなんだろう」の報告をご覧ください(別ウインドウで開きます)
※「朽木地域意識調査」の結果をご覧ください(別ウインドウで開きます)
(1)3グループに分かれて、それぞれにお題を選択、チーム名もつけました。
「田園風景を残したい」(田園風景チーム)
「栃餅を残したい」(栃餅チーム)
「何を残すのか」(針畑チーム)
人口減少、高齢化、技術の進歩、気候の変化など、推測される未来に関するデータを地球研の熊澤さんから説明していただきました。

・インターネット回線が広がり、働き方が変わる
・ドローンや自動運転技術が確立して、物の輸送、人の移動が変わる
・ロボット技術や自動化が進み、農業や工業の生産が変わる
・3Dプリンターで、必要な物が誰でも、どこでも作れる
・体内埋め込み型センサーが普及し、健康管理や情報管理が変わる
・シェアリング技術によって、車や機械などのシェアが広がる
限られた時間でしが、それぞれのグループでストーリーを考えて、最期に発表していただき、発表されたストーリーについて質問していきました。
(2)ストーリーの発表
「田園風景を残したい」
2047年、京都在住のIT企業に勤める青年が、小浜での海水浴の帰りに、てんくう温泉に立ち寄った。そこで、温泉の受付にいた3歳年上のエルさんに一目ぼれ。どうしても一緒になりたいと思いました。
エルさんは、大農家の一人娘さん。外へ嫁ぐことはできません。うちに来てもらえるなら一緒になれるのだけれど・・・ということで、青年は結婚を機に朽木へ。IT企業の勤めは継続しながら、農業も始めました。
この時代の農業は、IT技術とドローンを使って、生育の管理などができるようになっており、仕事と農業の両立も十分できます。米は高級ブランド米として販売できています。ドローンでの大規模な管理と箱庭的な水田の風景になっていますが、田園風景は残ります。
質問1) 大農家の設定はなぜ?農業を継続するには大地主でないと無理だから?
朽木では大地主はおられますか?
回答1) 人口が減り、農業から離れる人も多くなり、結果的に栽培を請負うなど農業
経営者に土地が集約されて大地主になったと設定しました。
質問2) てんくう温泉は残っていますか?
回答2) 朽木観光のメイン私設であり、もし湯が出なくなっても、また掘って継続して
いるかな。
質問3) ドローンでの栽培と箱庭的な田園風景と設定されたわけは?
回答3) 大規模な農業でドローンで管理する所と朽木らしい小規模な農業の風景も
残したいという、二刀流で考えました。
「栃餅を残す」
時は2017年。栃餅を生産する家に生まれたオーくん。好青年で家業も熱心に手伝っています。高島市で開催された婚活パーティーで、ある女性と仲良くなりました。その女性は朽木が大好きで、何度も朽木に来ており、栃餅も大好きでした。
この女性との出会いでオーくんの人生が大きく変わります。オーくんは退職して、栃餅づくりに専念することにしました。
トチの実が減っている現状に対しては、トチノキの植林を始め、量を増やしていきました。実を拾う時期や実のつき具合などは、ドローンで管理しています。拾う作業もドローンで作業できるように開発されています。アク抜き用の広葉樹林の灰も減少していますが、少ない灰でアク抜きできる方法を研究します。杉などの灰でもアク抜きできる研究も進めます。さらに、全く異なる方法で、灰を使わずにアク抜きする研究も進めています。
栃餅の生産工場はロボットで生産しています。栃餅以外にも多種類の餅を生産し、雇用も増やしています。
質問1) 植林をするのはだれですか?どこに植えますか?
回答1) 雲洞谷の大谷で植えます。オーくんが植えますが、地元の林業家と一緒に
植えています。例えば、新旭の針江のような湧き水を利用している人が水源
の森の植林に協力するとか、いろんな人を巻き込んで植林をするイベントな
ども実施します。オーくんが得意なことでもあります。
質問2) アク抜きの研究は自分でしますか?
回答2) 大学研究者などと一緒に、針葉樹の灰を使うとか、全く灰を使わないアク抜
きの方法などを研究できればと思います。現在は灰が減り、灰を集めるため
に薪ストーブユーザーからもらったり、外部から購入している状態ですので。

「針畑に残るもの」
なかなかストーリーにはならなかった。
今の針畑地域では、60代で退職後に針畑へ戻ってこられた人が最も若い。30年後の針畑は、針畑で生まれ育った人は一人もいなくなるのが現状です。そうなると従来の集落の延長線上の地域は無くなっていると言えます。従来の集落のように、血のつながり、地縁のつながりで生きている人が住む地域は無くなっていると思われます。従来のような集落が無くなっている状況の中で「何を残していくのだろう」と考えました。
何が残せるのかと考えると、文化的な行事が残こせるのではと思いました。
六斎念仏は、現在、継承者の孫世代が引き継ごうという機運が高まっていると聞いています。おそらく、継承されていくだろうと思いますが、それはその地に暮らし、住んだ人が継承してきた形とは異なる形での継承になるでしょう。
針畑地域の30年後には、どんな暮らしがあるだろうか?これまでのコミュニティのあり方とは異なるものになると思われ、どんな人が住んでいるか?、産業も何が残っているのか?と、想像ができない感じでした。
針畑に住もうと考え、移住する人は、多様な価値感を持っているだろうと想像されます。多様な価値感を持つ人々が、さまざまに関心を向けながら住む地域社会となるだろうと思われます。その中で核になり、生き続けるものは「小学校」ではないかと思います。
30年後も小学校が人を寄せ付けるきっかけになるのではと考えました。この針畑地域で子どもを育てたいと思う人が暮す地域になるのではと思います。それぞれの生活基盤や仕事を外部に持ちながら、小学校で子どもを育てたい人が集まる地域となるかもしれない。
ところが、30年後の小学校の形態は大きく変わっているかもしれません。
はたして、30年後に朽木西小学校は残っているのか・・・というところまで話していました。
質問1) 他のチームの方へ質問したい。針畑地域で30年後に核となるような産業
は想像できますか?針畑では水田が小さく、集約化も難しいと思います。
回答1) 米は針畑地域のブランドになっているので、集約化して農業は継続できるの
ではないかと思います。
針畑チーム) 一部の有機農業生産米は高くなっているが、全部ではない。
針畑は福島県くらいの気候らしいが、温暖化の影響があり、今後の生
産がどうなるか・・・。
鯖街道観光は、注目されていますが、生活を支えるほどになるかは、
難しいかな。
限られた時間での勉強会で、参加された人たちにとって30年後の地域を考えるのは難しいという感想をいただきました。
実際に、参加者を募って未来へのストーリーづくりをする場合は、じっくりと話せる時間を取る必要があることが分かりました。
またこの後、朽木地域で活動する市民グループに会いに行き、朽木らしさや未来に残したいものやことなどを聞き取り、みなさんから聞いた内容もストーリーづくりの素材にしていくことにしました。
11月の朽木文化祭では、地域の女性グループが演劇「お笑い水戸黄門」を発表されましたが、この勉強会の「栃餅を残したい」で考えられたストーリーを参考にシナリオを作られたそうです。
朽木の未来へつなぐ物語づくり報告(その2)へ続きます(別ウインドウで開きます)
Posted by たかしま市民協働交流センター at
15:33
│たかしま・未来・円卓会議報告
朽木地域意識調査まとめ~400人の朽木への思い~
2018年02月22日
朽木地域意識調査まとめ
~400人の朽木への思い~
~400人の朽木への思い~
たかしま市民協働交流センターは、朽木住民福祉協議会のみなさんと一緒に、朽木住民福祉活動計画を具体化するための取り組みとして、2015年度より「朽木のみんなと円卓会議」を実施してきました。
2015年度は、朽木地域の多様な世代の人々が地域のことを話せる場づくりをめざして、若者との円卓会議をしたり、安心して対話を楽しむ体験会を開いたり、朽木の伝統保存食である「へしこ」を使って「朽木にずっと伝えていきたいものってなんだろう」と題して対話をする場を持ちました。
これまでの経過はこちらでご覧いただけます(別ウインドウで開きます)
2016年度は、昔の写真と現在の暮らしや行事、地域の風景などを比較して対話する「朽木でずっと残していきたいものってなんだろう、世代をつなぐ朽木の今昔写真」を市場地域と針畑地域で開催しました。

また、2017年3月には朽木地域の中学生以上の住民の方を対象に、地域へのこれからや課題などについて意識調査を実施しました。
アンケートは、朽木住民福祉協議会と朽木のみんなと円卓会議の運営に参加されている琵琶湖環境科学研究センター、総合地球環境学研究所、大阪大学、立命館大学の研究者の方と一緒に作成しました。
調査票




画像をクリックすると大きくなります。
配布は高島市朽木支所を通して、各自治会長さんから全戸配布していただきました。
朽木中学校では、クラスルームの時間などで全員に回答していただきました。
また、結果のまとめは大阪大学の上須道徳さん、自由記述のまとめは立命館大学の小野 聡さんにご協力いただきました。
2017年3月に朽木地域で実施しましたアンケート調査「朽木地域意識調査」のまとめを報告します。
人口約1900人の朽木地域で、中学生以上の詳細に人数は把握できなかったのですが、自治会から全戸へ中学生以上の家族人数分の調査票を配布いただきました。また、朽木中学校では各クラスで回答していただき、ほぼ全員が回答してくれました。
約400名の幅広い年代と職業の方から回答からいただきました。
回答結果を見ながら、朽木のこれからについて考えるきっかけになればと思います。
回答者の年代別の割合
60代以上の方が60%でしたが、10代からそれぞれの年代の方が回答しています。
10代13%、20代2%、30代6%、40代8%、50代11%、60代25%、70代35%でした。
画像をクリックすると大きくなります。
回答者の職業
公務員2.5%、経営者2.0%、会社員14.1%、教育関係・研究職0.8%、自営業7.3%、農業・林業6.6%、専業主婦・主夫12.1%、
パート・アルバイト11.9%、その他1.0%、無職・年金28.8%、中学生12.9%、高校生0%
画像をクリックすると大きくなります。
質問内容
地域への愛着、地域の問題、活動などに関する問いです。
●あなたの住む集落や地域にこれからも住み続けたいとお考えですか?
●自分たちの子どもや孫たちの世代にもあなたの住む集落や地域に住み続けてほしいと思いますか?
●あなたの住む集落や地域に愛着を感じていますか?
●自分たちの子どもや孫たちの世代にもあなたの住む集落に愛着を感じてほしいですか?
●あなたの住む集落や地域にとって人が減っていることは重要な問題ですか?
●あなたの住む集落や地域にとっていくつになっても安心して暮らすことは重要な問題ですか?
●あなたの住む集落や地域にとって役所や市民団体の応援は重要と思いますか?
●地域を応援する活動に参加したいですか?
●今、あなたがしている地域の応援につながる活動があれば教えてください。
朽木地域の将来についての問いは下記になります。
●あなたの住む集落や地域は、2050年に暮らしやすいところになっていると思いますか?
●あなたの考える将来の不安を二つ教えてください。
●金銭的に豊かな生活を送ることは重要ですか?
●人間関係が豊かで、顔の見える関係で生活が送れることは重要ですか?
●伝統行事や食文化が伝えられていくことは重要ですか?
●集落や地域に人が住み続けていくことは重要ですか?
●子孫や未来の人たちに集落や地域の大切なものを残しておくことは重要ですか?
●集落や地域に残していきたいものを二つ書いて下さい。
集計結果です。
あなたの住む集落や地域にこれからも住み続けたい
少しそう思うと非常にそう思う、をあわせると55%
画像をクリックすると大きくなります。
自分たちの子どもや孫たちの世代にもあなたの住む集落や地域に住み続けてほしい
少しそう思うと非常にそう思う、をあわせると31%
画像をクリックすると大きくなります。
地域への愛着に関して年齢では大きな差は見られません。
どの年代も60%以上の方が愛着を感じていると回答
画像をクリックすると大きくなります。
あなたの住む集落や地域にとって、人が減っていることは重要な問題だと思いますか?
非常にそう思うと少しそう思う、をあわせると86%
画像をクリックすると大きくなります。
あなたの住む集落や地域にとって、いくつになっても安心して暮すことは重要な問題だと思いますか?
非常にそう思うと少しそう思う、をあわせると87%
画像をクリックすると大きくなります。
まとめてみると、
●約半数の方が朽木や自分の集落についてこれからも「住み続けたい」と考えています。
●約7割の方が朽木や集落に愛着を持っています。
●これらの回答には年齢などは関係ないようです。
●しかし、自分の子供や孫(いない方は「いる」とすれば)に、これからも朽木に住み続けてほしい、と考える方は3割に減ってしまいます。
●他の理由(彼らの選択肢を減らしたくない、など)もあるかもしれませんが、朽木や集落全体で人が減っていることが不安につながっていることが原因ではないか、と考えられます。
自由記述の内容から考えてみます。
これからも朽木に住み続けたいと思いますか?(60代以上の方の回答)
「住み続けたいと思う」と回答した方の自由記述
<住み慣れる>
・慣れ親しみ知り合いの多い朽木で住み続けたい
・住み慣れたところで住み続けたいが、買い物や病院への通院に一人になったとき、車で出かけられなくなったときのことを思うと不安
・長年住み慣れている、今の生活に満足
・高齢になり生活をして行くには少し不安を感じるが住み慣れた場所でいつまでもいられたらと思う。
・土地になれたから
・利便性が悪いが住み慣れないところで住みたくない。
<ここ以外考えられない>
・ここ以外考えられないから住み続けたい
・ここの場所がよい
・他の土地へ行くにも高齢のためここに住み続けたい
「地域への愛着の理由」には、
<先祖代々の土地>
・先祖代々守ってきた土地がある
・生まれ育った所と先祖代々が受け継いでこられた物がたくさんあるから
・先祖代々の土地 友達がいるから
<地域のつながり>
・地域のつながり、助け合いがある
・地域のつながりが強いので
・地域の人と気軽に話せる
・近所づきあい 困ったとき等助け合いなど、とても助かっている。地域の事業者もみな一生懸命やって盛り上げてくれている
・地域の人々が親切 など
生まれ親しんできた地域とのつながりの重視、愛着が書かれていました。

画像をクリックすると大きくなります。
これからも朽木に住み続けたいと思いますか?(60代未満の方(中高生除く)の回答)
「住み続けたいと思う」の自由記述
<地域の温かさ>
・祖父母の同居 お墓の管理 地域住民の人がら 地域住みやすい
・どこに住んでもそうなのかも知れないが、地域や集落に住んでいる人のあたたかさ等でそのように思うのかも
・住み慣れているから 環境が良く干渉されない
・毎日が心地よく生活できているかた住み続けたい
<子育て、環境>
・子育てにすばらしい環境だと考えるため、また自分たちの終の住みかとしても
・子どもと住むのに適した環境だと思うから
・通勤通学、買い物通院には不便だが近所付き合いが密で安心して過ごせる 子どものことも見守ってもらえて助かる 自然豊かな環境も好き
「地域の愛着の理由」では、
<農村的価値>
・豊かな自然と人の温かさ
・自然に恵まれた所であること、近所の人達とのつきあい
・移住者を受け入れてくれる人。助け合う近所関係。少なくても地域で子ども達を見守り育てる環境。自然環境。
・自然(動植物)と近い距離に集落があるので毎日新しい発見があること
・人がらのよさ、住みやすさは(安曇川への道も便利になった)特によいわけではないが自然のうつりかわりがよい
・自然豊か、近所づきあいに適度な距離
・豊かな自然が残っている いい人ばかり
・自然豊かなこと 顔の見える付き合いができること
・自然豊かなところ 知っている人たちが多く人々とかかわりながら生活できていること など
地域のつながりへの実感、環境のよさが書かれていました。

画像をクリックすると大きくなります。
これからも朽木に住み続けたいと思いますか?(60代以上の方の回答)
「住み続けたいとは思わない」と回答した方の自由記述
<雪>
・高齢になるにつれ、冬の生活、雪除け、外出等が不安 高齢者向けの体操教室などの多様な教室が少ない
・大雪
・これだけ雪が多いと苦になる
・人口減少 雪対策
・冬季の雪等高齢生活が不安
・高齢者には住みにくい(雪害、獣害)(土地管理)
・冬寒さが厳しく雪に埋もれると極端に活動が制限されることがいや
<車>
・生活が不便 高齢となり買い物通院等自動車をしようする場合
・車に乗れなくなれば買い物通院に不便 老人一人暮しでも順番だからと区の役をしなくてはならないこと
・車の運転ができなくなったからとれも不便で生活しにくい
・車に乗れなくなったと同時に生活が困難になる
「地域で必要な支援はなんですか?」
<つながり、サポートの不足感>
・健康サポート
・人口増加のための施策 一人暮し支援
・通院、買い物など 冬季の除雪作業
・隣近所が離れている 何か事故があったときに連絡の取れるようなシステムがあればよい
・日常的に隣近所の声かけ
・災害時の対応が遅い
・介護施設を増やして入居希望者をできるだけ受け入れてもらいたい
・見守り 声かけ地域の和 など
歳を重ねることによる、雪への対応・車運転への不安が書かれていました。

画像をクリックすると大きくなります。
これからも朽木に住み続けたいと思いますか?(60代未満の方(中高生除く)の回答)
「住み続けたいとは思わない」と回答した方の自由記述
<現在の不便さ>
教育
・子育てするには良いけれど、生活が不便だから。(環境的に)子どもができたとき、学び合いができないから。
・生活の不便 子どもクラブなど種類に少なさ、習い事がしにくい
交通
・交通が不便だから、買い物が遠い
・病院、スーパーが遠いから
<将来ビジョン>
老後
・年をとると生活に不便な地域だから
・老いてからの生活が不安だから(買い物、雪かきなど)
・その時々の生活環境に応じて変わる可能性
<人口・高齢化>
・周りに若い人がいなくてお年寄りばかりだから 20代30代の夫婦が周りにいない
・不便 区の行事に行っても人が少ない
・不便 少子高齢化が深刻で将来が心配
「将来への不安」についての回答は
<高齢化社会での生活>
・近親者の介護
・地域からの期待(若者に対する)
・人口減少による子どものいない地域
<現在的な不便さ>
・冬場の生活(雪かき、屋根の雪下ろし)
・大雪時の除雪
・交通の便の悪さ
・交通手段
地域現状への不満・将来的な縮小への悲観が書かれていました。

画像をクリックすると大きくなります。
子どもや孫たちの世代あなたの住む集落に愛着を感じてほしいと思いますか?
「思う」と回答した方の自由記述
<人>
・豊かな自然と人の温かさ
・人つき合いが良い
・子どもの頃から慣れ親しんだ風景と人と人のつながりが好きだから
・移住者を受け入れてくれる人 助け合う近所関係 少なくても地域で子ども達を見守り育てる環境 自然環境 水や食べ物
・自分が子どもだったとき(保~中学生)は縦や横の学年のつながりが強く、とても良い人間関係が育てたから 自然がいっぱいあって好き
・周りの人の温かさと自然
・住み慣れた土地や人と人のつながりある
<土地・地縁>60代以上の方の記述が多かった
・先祖代々守ってきた土地(地域)があるから
・生まれ育った土地だから
・住み慣れた土地や人と人のつながりがある
・昔からの人のつながり 顔の見える生活 守ってきた土地等
・土地が広いく住みやすい
・収入と結びつかないが守ってきた土地だから
「集落や地域に残したいものはなんですか?」では
<地縁的文化への誇り>
・もちつき
・行事/伝統の祭り/地域の行事
・食文化は次世代につないでいくことはたいへん大事
・伝統文化の語り継ぎの育成
・人と仲良くすること
<人のつながりへの誇り>
・義理人情
・隣組組織を残し、お互い様として日常のかかわり
・人の和
・互助、共助の精神
・親から子への考え方は地域に根づくものである
・田舎の人間関係のよい部分
・地域住民の子どもを残しておくこと
・人間関係の豊かさ
・先祖 など
人・土地とのつながりがアイデンティティに直結していることが書かれていました。

画像をクリックすると大きくなります。
子どもや孫たちの世代にもあなたの住む集落に愛着を感じてほしいと思いますか?
「思わない」と回答した方の自由記述
必要な支援について
<雪・除雪>
・冬場の除雪
・医療機関の充実、除雪
・有害鳥獣 雪害対策 現状維持を応援
・冬季において雪が多いときの支援
・交通の便(タクシー、バス、除雪や除草)、水田管理
・通院、買い物など 冬季の除雪作業
・個々の家屋の除雪の応援 獣害対策
・運転できなくなった後の交通手段 除雪
<人々の住みよさ>60代未満の方の記述が多かった
・どうすれば安心して暮せるか?や元気に暮せるか?などいろいろな考え、意見をその立場にあった人に直接、意見やサポート、相談できる事が大事だと感じる
・弱い立場の人々を最優先に生活に密着した応援
・個人ではどうすることも出来ないようなことが出来たときに臨機応変に対応してもらえるような応援を
・人口減に伴う地域住環境の整備と維持の困難のためのサポート(集落内の種類の普請がいつまできちんとできるのか)
・老人だけの家庭の支援
気候への対応、住みよさの維持に対する公助の限界意識が書かれてました。

画像をクリックすると大きくなります。
まとめてみると
●年配者は先祖代々の土地への思い、地域のつながりに対する安心感から、朽木への『慣れ親しみ』を感じていて、朽木に住み続けたいという思いの方が多いことがわかりました。
●一方で、60代以上の方にも住み続けたくないと思う人もいます。そうした人々は、『車を使うこと・使えなくなること』や『雪への対策』について周りからの支援を得られないことに不安を感じている傾向にありそうです。
●また、中高生を除く60歳未満の人々にも、住み続けたいとは思わないとする回答する人たちがいました。60代以上と同様に雪の中での生活の不便さ、教育面での不足点、また自らが高齢になったときの生活の不便さから、消極的な回答が生まれている傾向があります。
●一方で、60歳未満の人々の回答にも、地域の暖かさや子育て環境に魅力を感じて、住み続けたいと思う人も多いことがわかりました。
●大切な点は朽木に『子育て・環境』面で魅力に感じている人がいて、住み続けたいと思わないとの回答の傾向と正反対のものが出ていることです。
●農村の中での教育に魅力を感じる若い世代にとって、朽木は住みよい町になっています。
●私たちにとってすべきこと、できることは何でしょうか?
調査結果については、
2017年11月の朽木文化祭での発表をはじめ、朽木住民福祉協議会の方々、生活支援ボランティアでんでん虫の定例会、NPO法人麻生里山センターの方々、高島おさんぽ会の方々、きりかぶの会の方々、睦美会の方々、朽木支所のまちづくり担当者、朽木中学校の先生などです。
まだまだ多くの方にお伝えしたいと思っています。
そして、朽木地域のみなさんとこれからの朽木地域のことをお話する機会を持ちたいと思っています。
調査結果についてのお問合せ先
たかしま市民協働交流センターへ
〒520-1622 高島市今津町中沼1-4-1(今津東コミュニティセンター内)
TEL 0740-20-5758
FAX 0740-20-5757
E-mail webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp
HP http://tkkc.takashima-shiga.jp/
タグ :朽木のみんなと円卓会議
Posted by たかしま市民協働交流センター at
17:22
│たかしま・未来・円卓会議報告
【9/9】たかしまの森へ行こう!2017 第2回勉強会~朽木雲洞谷のお母さんに、栃ノ実の話を聞きに行こう~開催報告
2017年10月06日
たかしま・未来・円卓会議2017
たかしまの森へ行こう!第2回勉強会
たかしまの森へ行こう!第2回勉強会
朽木雲洞谷のお母さんに、
栃ノ実の話を聞きに行こう
栃ノ実の話を聞きに行こう
開催報告
※画像をクリックすると大きくなります。
話題提供/朽木雲洞谷在住 山下露子氏
巨木と水源の郷をまもる会 小松明美氏
摂南大学講師 手代木功基氏
日 時/9月9日(土)9:30~14:30(受付9:15 終了14:30)
集 合/山村都市交流館源流の駅「山帰来」
【高島市朽木中牧528】
イベントの案内はこちら。
たかしま市民協働交流センターでは、平成25年度より、さまざまな主体が協働で課題解決に取り組むまちづくりを目指し、「たかしま・未来・円卓会議」を開催しています。
これまでのたかしま・未来・円卓会議(森へ行こう!PJ)の報告はこちら。
そして、平成26年度「たかしま未来円卓会議」を通じて、今取り組むべき地域課題のひとつとして「放置された森林」があげられました。
そこで、「たかしまの森へ行こう!プロジェクト」では、課題となる森林を地域資源と捉え、様々な角度から森林にかかわる団体・企業・個人をネットワーク化しながら、様々な森林資源の活用について、体験型の勉強会を開催しながら、新しい森林の魅力に気付くきっかけづくりをしています。
たかしまの森へ行こう!ポータルサイトはこちら⇒https://www.takashima-mori-go.net/
今回のテーマは栃の実!
朽木の特産品と言えば、栃餅、鯖寿司、へしこがすぐに思い浮かびます。特に栃餅は森林を地域の人々が活用し、受け継がれてきました。
しかし、栃餅をつくる方の高齢化・栃の実の鹿の食害など聞かれる中、少しずつ栃餅を地域に残していくことが難しくなっています。
今回は、栃の実をとおして森林と私たちの持続可能な関係を考える機会にしたいと思いました。
午前中は生杉で栃の実拾いを通じて、巨木と水源の郷をまもる会の小松明美さんからお話をいただき、午後は、栃の実を今も実際に生活に取り入れて過ごされている山下さんにお話を伺いにいきました!また、栃の木の現状について、摂南大学で栃の木の研究をされている手代木功基さんからも、お話を聞かせていただきました。
朝9:30に朽木の山帰来に集合して、まずは栃の実拾い体験!
栃の実拾いの場所は、栃の木とブナの木の原生林!
ここは県の公園指定場所でもあり、びわ湖淀川の源流でもある場所だそうです。谷間に木漏れ日が綺麗にさしており、とても神秘的な場所でした!
栃は鹿など山の動物にとっても貴重な食材です。既に食べられて殻だけになった実もありましたが、全員で手分けして拾ってこれだけ集まりました!
栃の木は谷筋にはえる事が多いため、栃の実拾いは足場の悪い傾斜地で行うのですが、朽木では栃の実を加工している方が高齢化しています。高齢の方が、足場の悪い傾斜で、栃の実拾いを1人2人でやるととても大変です。
そこで、例年イベント形式で皆で拾うことで、栃の実の文化を伝えていきながら、無理なく継続・伝承していけるようにしたいと話されてました。
栃の実拾いが予定よりも早く終わりましたので、ブナの原生林を皆で歩いて見学しました。
ブナの木は、今ではだいぶ数も減ったそうですが、それでもいたるところに大きなブナの木がありました。秋になると綺麗な紅葉景色になるそうです。
公園内はいつでも自由に歩くことができます。皆さんもぜひご覧になってください。
昼食は山帰来に戻りお弁当を食べた後、地元の野菜や手作り品を見てまわりました。
地元の野菜の他にも、地域の木材を使った工芸品なども販売されていました。僕も木のマウスパットを買いました♪
午後からは雲洞谷へ移動して、講師の山下さんの家で栃の実の皮むき体験!
栃の実を食べられるように加工するには、①虫取り ②天日干し ③水さらし(ふくらまし) ④皮むき ⑤水さらし ⑥加熱 ⑦灰合わせ(あく抜き)といった手順があります。
今回は、④皮むきの体験と、⑦灰合わせの見学をさせていただきました!
栃の実の皮むきは「とちへし」と呼ばれる道具を使って、むいていきます。
木の端でこすりあわせるようにむくのですが、想像以上に難しい!
皆さん、最初はなかなか上手くいきません!山下さんや巨木と水源の郷をまもる会の皆さんいわく、皮むきと言っても、固い殻をむくので、殻を割るくらいに力を入れて思い切ってやることがポイントだそうです。
そして、コツをつかんでどんどん作業が早くなっていった皆さんのおかげもあり、すべての栃の実の皮がむき終わりました!
栃の実の皮むきが終わったら、水さらし・加熱のあと、灰合せ(あく抜き)をします。
この時の灰の量が大事!栃の実をおいしく加工できるかどうかは、この灰で変わると話されました。
栃の実はあくが本当に強く、これだけの灰を入れて、やっと栃の実のあくがぬけるんです。あく抜きなしだと、渋くてにがくてとてもじゃないけど食べられないそうです。
現在、この灰を集めるのに苦労されているそうです。
灰は、広葉樹の灰を使います。昔はどの家でも薪を使っていて、灰が地域にたくさんあったそうなのですが、今では薪を使う家庭も減っていて、灰が足りなくなっています。
薪ストーブなど使う方で広葉樹の灰があれば、灰を残して置いてほしいとのことでした。
「家に広葉樹の灰があるよ!」「家で定期的に広葉樹の灰ができる」という方は、ぜひご連絡ください。
たかしまの森へ行こう!プロジェクト 事務局(たかしま市民協働交流センター)
TEL:0740-20-5758 mail : webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp
たかしまの森へ行こう!HP : https://www.takashima-mori-go.net/
山下さんは、栃餅をつくるお父さんの手伝いをし始めた27年ほど前から、栃の実の活用に取り組まれているとのこと。
最初は慣れないことでなかなか上手くいかなかったそうですが、今では生活の一部になって、自分の生きがいになり楽しくなっていると話されていました。
皮むきが一通り終えると、皆で栃餅を食べながら勉強です!
①栃の木の巨木は朽木で400本近く認定されている
巨木とは、木の幹の周囲が3メートル以上の木の事を指します。
もともと関西で90本ほどしか確認されていませんでしたが、巨木と水源の郷をまもる会による朽木地域の巨木調査で390本以上の巨木を確認!そのほとんどが、川の近くの傾斜部分と最上流部分に生育していたそうです。
②栃の木(巨木)は川辺にはえてくると、研究で推測。
栃の木は、川の近くの水気のあるところにはえるそうです。しかし、川の本当に近くにはえるのではなく。川から5~10メートルほど離れたところにはえているのがポイント。もともとは、川のすぐ近くにもはえていたが、洪水等により流れてしまうことが多く、少し離れた場所の栃の木が残るのではないか?とのことでした。
③朽木の巨木は里山に生育する!
「巨木」と聞けば、人が入れないような奥山の奥に、生育しているイメージがありますが、朽木の栃の巨木は人々が利用する山林に生育しています。積極的な山林の利用により、栃の木は地域の人々に選ばれて、残されてきたそうです。
栃の巨木は、誰も立ち寄らない自然の中で育まれたのではなく、朽木の自然環境に支えられ、地域の人々との関わりや地域外との関係の中で生き続けている「文化的な遺産」なのです。
今回の勉強会で感じたことは、森を活用するには、森に入ること!
朽木の巨木もそうですが、人が森(山林)に入ることではじめて活きてくることも多いのだと学びました!
~~これからも、たかしまの森へ行こう!では、森林の様々な活用をテーマに、
楽しく、そして学びある勉強会を開催していきたいと思います~~
楽しく、そして学びある勉強会を開催していきたいと思います~~
以上、報告は三上でした。
タグ :森へ行こうPJ
Posted by たかしま市民協働交流センター at
16:01
│たかしま・未来・円卓会議報告
【7/22】たかしまの森へ行こう!2017 第1回勉強会~森林の新しい活かし方「森林セラピー」を体感しよう!~開催報告
2017年08月23日
たかしま・未来・円卓会議2017
たかしまの森へ行こう!第1回勉強会
たかしまの森へ行こう!第1回勉強会
森林の新しい活かし方
「森林セラピー」を体感しよう!
「森林セラピー」を体感しよう!
開催報告
話題提供/自然セラピー案内人の会 桑原喜平氏
日 時/7月22日(土)9:30~14:00(受付9:00 終了14:00)
場 所/マキノ高原【高島市マキノ町牧野931番地】
イベントの案内はこちら。
たかしま市民協働交流センターでは、平成25年度より、さまざまな主体が協働で課題解決に取り組むまちづくりを目指し、「たかしま・未来・円卓会議」を開催しています。
これまでのたかしま・未来・円卓会議(森へ行こう!PJ)の報告はこちら。
今回の勉強会のテーマは「森林セラピー」
今までは薪や食べものなど、「モノ」の資源に着目していましたが、今回は「場所」としての資源として活用される「森林セラピー」について勉強会を開催しました!
まずは参加者の皆で集まって名札を配られて自己紹介。
ここからもう、森林セラピーがスタートしています!まずは配られた名札に注目。その名前は「くま」や「いのしし」、「ひつじ」など、動物の名前が書かれていました!
講師の方いわく「別世界の体験をしてほしいので、今から自分の名前でなく、動物の名前で呼び合います。」とのこと。
次に森林の中で準備運動にストレッチ。木の陰の下で、身体を慣らします。
草原を歩き、山道を歩いていきます。
草原では、「身体への感覚を感じてみる」ということで、
①後ろ向きに歩く ②目をつむって歩く
ということをしました。
普段と違う歩き方をすることで、普段は使わない(ひらいていない)感覚を開いていくとのことです。
山の木漏れ日の中、ゆっくりと歩いていきます。
途中の川で、冷たい水につかって休憩したり。木陰があれば休憩したり。
山登りと違い、森林セラピーは「〇〇時までに頂上に着く」「知識を得ながら歩く」ということはしません。
森林の中にあるものをそのまま感じながら自分のペースで歩き、頂上を向いて歩くのではなく、周りの景色をゆっくり楽しみながら歩いていきます。
森林セラピーは、「身体の運動」でもありますが、メインは「心の運動」。心理療法(セラピー)になるのだと感じました。
そして、頂上近くの滝「調子ヶ滝」に到着!
皆さん、子どものようにはしゃいでいます。
滝を背景に、記念撮影もしました。皆さん、とても良い笑顔です。
下山途中ではマットで瞑想。その後、寝転がって一休み。森林の恵みを体で感じとります。
下山したら、たかしまの地域食材をふんだんに使った「高島トレイル弁当」を食べながら、勉強会スタート!
対話形式で始まった、ざっくばらんな勉強会。
出てきた話は、以下の通りです。
①今までに森林セラピーに来られた方は何人くらいですか?
来られる方はあまり多くはない。毎回定員を15名に設定しているが、満員になったのは数えるほど。
特に高島市の方は来ることが少ない。近くに住んでいるからこそ、その魅力に気付いていない方が多いとのことでした。今回の参加者の中でも、マキノ在住でありながらマキノ高原のセラピーロードを初めて知ったという方がおられました。
ただ、今まで参加された延べ人数で言うと100名以上はいると思うとのこと。
②森林セラピーをいつからされてますか?
森林セラピーが高島市へきたのは約9年前。平成20年に高島市にセラピーロードが認定され、そのころからセラピーの研修に参加しながら、案内人を続けているとのこと。セラピー体験会を始めたのは3年ほど前のこと。
③途中、ヨガマットで瞑想をしましたが、森林の中でやるとどんな効果がありますか?
瞑想自体は、実はどこでもできます。ただそれは、瞑想することに慣れた方(何処でも神経を集中できる方)だけ。普通なら周りの雑音が気になって集中できない。
その点、森の中であれば川の音や木々が風に揺れる音、自然の音の中のみ。静かな空間で誰でも神経を集中させやすいため、瞑想に向いているとのこと。
④ストレスには2種類ある。「良いストレス」と「悪いストレス」
森林セラピーに来て欲しいのは、仕事や家事など、日常的にストレスを感じる若い方。しかし、「ストレス」というものを十分に理解されている方が少ないように感じる。目標を持って課題を持つことは良いストレス。ただ疲れを感じるのは悪いストレス。日常の出来事を「良いストレス」にすることが大切だと思う。森林セラピーを通して、自分を見つめ直す事ができると良いと思う。
「若い方」というターゲット層で、主婦の方も対象に考えていきたいが、子ども連れの方は難しい。(子どもは発達段階や個性に差がありすぎるため、セラピーが難しい。集団となると更に難しくなる)
現段階ではやっと小学4年生までお子様連れをOKできたところ。
⑤セラピー「コンダクター」(導く人)とは、何に導くことが目的なのか?
森林セラピーで導くのは「人間の本来の感じる力」。しかし、その「人間本来の感じる力」は今、失われつつある。
山には水があり、綺麗な空気がある。山菜など食べものも多くある。山で生き物が生まれ、海では生き物が育まれる。
古来、海と山は「母なる海。命を産む山」その中に人間が本来持っている力を見つけるアクセスがあると考えている。
最後に講師の桑原さんは、「高島には素晴らしい環境がまだ残っている。これを使わない手はないと思う。」と、高島の恵まれた環境について再度話されました。
たかしまの森へ行こう!では、これからもたかしまの森を様々な角度から楽しみ、学べる勉強会を開催していきます。
次回は9月9日(土)、朽木雲洞谷にて「栃ノ実」をテーマに開催いたします。
是非ご参加ください。
次回は9月9日(土)、朽木雲洞谷にて「栃ノ実」をテーマに開催いたします。
是非ご参加ください。
以上、報告は三上でした。
タグ :森へ行こうPJ
Posted by たかしま市民協働交流センター at
10:01
│たかしま・未来・円卓会議報告
朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう 針畑地区の取り組みまとめ
2017年08月09日
2106年10月~2017年2月に実施しました
朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう(針畑地域)のとりくみをポスターでまとめています。
画像をクリックすると大きくなります。
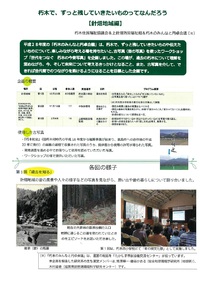
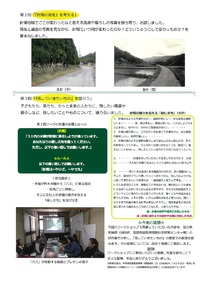
2016年10月開催の 朽木でずっと残していきたいものってなんだろう
第1回「昔の写真を見ながらお話しましょう」もご覧ください(別ウインドウで開きます)
2016年11月開催の 朽木でずっと残していきたいものってなんだろう
第2回「針畑地域でここが変わったなと思える風景や暮らしの写真を持ち寄り、お話しましょう」もご覧ください(別ウインドウで開きます)
2017年2月開催の 朽木でずっと残していきたいものってなんだろう
第3回「残したい風景や暮らしなど、朽木で残したいことやものについてお話しましょう」もご覧ください(別ウインドウで開きます)
朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう(針畑地域)のとりくみをポスターでまとめています。
画像をクリックすると大きくなります。
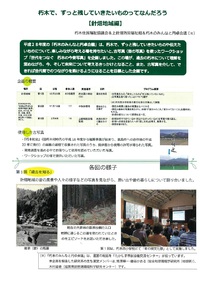
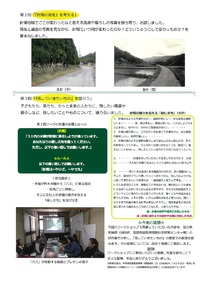
2016年10月開催の 朽木でずっと残していきたいものってなんだろう
第1回「昔の写真を見ながらお話しましょう」もご覧ください(別ウインドウで開きます)
2016年11月開催の 朽木でずっと残していきたいものってなんだろう
第2回「針畑地域でここが変わったなと思える風景や暮らしの写真を持ち寄り、お話しましょう」もご覧ください(別ウインドウで開きます)
2017年2月開催の 朽木でずっと残していきたいものってなんだろう
第3回「残したい風景や暮らしなど、朽木で残したいことやものについてお話しましょう」もご覧ください(別ウインドウで開きます)
Posted by たかしま市民協働交流センター at
10:55
│たかしま・未来・円卓会議報告
報告!朽木でずっと残していきたいものってなんだろう 第3回残したい風景や暮らし、ことやものについてお話しましょう
2017年07月07日
たかしま市民協働交流センターの坂下です。
朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。
「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々は何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。
平成27年度からの経過は「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。
朽木の針畑地域で平成28年10月から3回、さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、昔の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。
2月6日(月)に朽木西小学校官舎で実施した、第3回「残したい風景や暮らしなど、朽木で残したいことやものについてお話しましょう」の報告を、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんからしていただきます。
開催案内はこちらをご覧ください。
京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。
平成28年10月から翌年2月にかけて針畑地域で実施した、古写真を使った3回のワークショップについてご報告します。
朽木で、ずっと残していきたい風景や行事や人のつながりなどについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう」を実施しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、現在、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真をとおして世代間のつながりづくりになることを目標として企画しました。
平成28年7月から9月に、市場集会所で実施した古写真を使ったワークショップは、朽木市場地区に近い地域の古写真を用いて、30代から70代の方々のべ46名が朽木に残していきたいものやことについて話をしました。
報告は下記のリンクからご覧ください。
「朽木でずっと残していきたいものってなんだろう 世代をつなぐ朽木の今昔写真」
第1回「昔の写真を見て語ろう
第2回「今の写真を撮って、昔の写真と比べてみよう」
第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」
をご覧ください。
10月29日に実施しました、第1回「昔の写真を見ながら、お話しましょう」の報告で、ワークショップ3回の構成や準備について掲載していますのでご覧ください。
11月19日に実施しました、第2回「針畑地域でここが変わったなと思える風景や暮らしの写真を持ち寄り、お話しましょう」の報告もあわせてご覧ください。
さて、第3回は、「『残していきたいもの』を語らう」を目的に雪降る中、朽木西小学校官舎にて16名の方にご参加いただき実施しました。
今回も案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員(現在は上級研究員)で歴史学が専門の 鎌谷かおるさんです。
地域に「残していきたいもの」とは何なのかを考えるために、前半、第1回と第2回で見ていただいた写真をふりかえり、今と昔の風景や人々の様子から「針畑は何でできているのか」を考えました。写真で切り取られたいろいろな「場面」とその変化から、針畑の方々がこれまで何とつながってきたのかに気づき、どのつながりを、どのように残していきたいのかを考えるためです。
写真は、「自然とのつながり」、「(針畑)地域内のつながり」、「(針畑地域と)他の地域とのつながり」、「人とのつながり」という視点から紹介しました。
写真で切り取られた場面を紹介しています。

後半は、「針畑の魅力をどうやって伝えるか」を考えました。
テーマを「未来の針畑で暮し、生きるかもしれない人たちに魅力を伝える」という設定でワークを行うことにしました。このような設定によって、参加者が「未来の針畑に残していきたいもの」を考えやすくなるのでは、と考えたからです。
また、誰に魅力を伝えるのか、伝える相手が具体的な方が考えやすくなりますので、「針畑に移住しようか迷っている若い夫婦に語りかける」と設定しました。夫婦が道の駅くつき新本陣から、不動産屋さんの用意した「バス」に乗り、各地区を訪ねて回ります。参加者は、自分が住んでいる地区にバスが着いたら、その夫婦に対して針畑の魅力を一言で伝える「殺し文句」を語りかける、ということにしました。
せっかくなので、少しでも臨場感を高めたいと、事前に道の駅から針畑地域をぐるりと回って大津市葛川梅ノ木町の国道367号線との交差点に至る道のりを動画で撮りました。まるで夫婦がバスから見ているように、道のりを映像で見ながら、各地区に着いたらその魅力を伝えていただきました。

参加者に示されたお題とルールは、以下に示す通りです。
さて、どのような「殺し文句」が語られたのでしょうか。
針畑の自然に注目して言葉を紡いでくださったのは、小入谷、中牧、古屋の各地区にお住まいの方々でした。合作で「殺し文句」を考えてくれました。
「針畑はちょっと不便やけど、自然が多いし、水も空気も美味しいよー・・・ま、雪は降るし、積雪は多いし、バスはしょっちゅう止まるし、せやけど、せやけど雪景色がきれい」。
3名の方々から紡がれた言葉は、不便さ、ときには動物による被害といったものと引き替えに、得られる自然の多さと美しさは変え難いといったものでした。
そして、針畑に住む上での目的や目標に注目した言葉を紡いでくれたのは、別の3名の方々でした。
たとえば、小入谷に住まわれている方が投げかけたのは・・・
「・・・・周りの環境、周りにある生活に、ある程度合わせたら別に問題ないし。そんで、自分がどういう思いでここへ住もうかな、住んでみようかな、と思って来たかという気持ちが、一番問題だと思うんですよね。・・・自分で好んでここに住むと」
「いろんな生活のことも、食事のことも、あるいは、車ないと住めへんとか、いろんなん(いろんなこと)あると思うけど、それらも全部踏まえて、やっぱり自分もこういう田舎を求めて、・・・住みたいなと思う人だったら、若くても十分住めると思うんですね」
「人それぞれ、いろんな目的があると思うのね。別に一から十まで田舎の人に合わす必要ないやろうし、自由気ままに住める。逆に言うたら、住めるところがここなんだ、と思うんですね・・・」
3名の方々から紡がれた言葉は、目的や目標を持っていることが大事で、ここでの暮しを選んだことを思って生活していけば、そんなに大変なことではないといったものでした。
発表の様子です。

朽木地域の最も奥の地域で、みなさん「~やけど」のニュアンスをどこかに含みつつ、若い夫婦に針畑の魅力をアピールしてくださいました。
終了後のアンケートでは、「全体にポジティブな話が多くあった。」とのコメントが寄せられました。確かにそのような雰囲気の中で語られた、それぞれの「殺し文句」だったと思います。その一方、「針畑の未来について良いイメージを描けない(こと)に残念な気持ち」とのコメントも寄せられました。紡ぎ出された言葉たちは、どんなにポジティブなものであっても、未来について良いイメージが描けないことと背中合わせの状況から生まれたもの。これをどのように受け止めて前に進めばよいのか、本当に難しい課題です。
今後のワークショップへの要望には、「新しい家族(移住者)たちがここで暮すことが、できるように何が出来るかについて話す場がほしい。」「話すだけでなく、この地域をいろいろ見る機会を作った方が良い気がする。」「他市町での事例も参考にさせていただきたい。」といったものがありました。
さて、果たしてみなさんの「殺し文句」は夫婦の心に届いたのでしょうか。夫婦が移住を決めたとすれば、それにはきっと理由があるはず。そして、それが分かれば、私たちがこれからすべきことが見えてくるのではないでしょうか。次には、これを探ることができるような内容のワークショップを企画していきたいと思います。寄せていただいた要望には、次の企画を考える上で重要なヒントがたくさん含まれているように思います。ぜひ活かしていきたいですし、一緒に考えていければ幸いです。
ワークショップで行ったこと、見えてきたことについて、5月21日(日)に高島市森林公園くつきの森の「ユリノキ祭」でポスターにして展示しました。
針畑地区での取り組みをまとめたポスターはこちらから見ていただけます。
最後になりましたが、ワークショップに参加してくださったみなさん、写真を貸し出してくださったみなさん、ありがとうございました。そして、今年度も引き続きよろしくお願いいたします。
主要参考文献
[1] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 通史編』, 高島市, 294pp.,2010
[2] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 資料編』, 高島市, 264pp.,2010
朽木住民福祉協議会と連携し、「朽木のみんなと円卓会議」を運営しています。
「安心していつまでも朽木で暮せる」地域のために、地域の人々は何ができるのか、どんな将来の朽木地域を描くのか、子どもも大人もともに考え、話し合う場づくりをしています。
平成27年度からの経過は「朽木のみんなと円卓会議」の取り組みをご覧ください。
朽木の針畑地域で平成28年10月から3回、さまざまな世代の人が朽木の昔を知り、今の朽木を確認し、これからの朽木について考える機会を、昔の写真や最近の写真など、写真を入り口にして取り組みました。
2月6日(月)に朽木西小学校官舎で実施した、第3回「残したい風景や暮らしなど、朽木で残したいことやものについてお話しましょう」の報告を、総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤さんからしていただきます。
朽木でずっと残していきたいものってなんだろう
第3回「残したい風景や暮らしなど、朽木で残したいことやものについてお話しましょう」
第3回「残したい風景や暮らしなど、朽木で残したいことやものについてお話しましょう」
開催案内はこちらをご覧ください。
京都は北区の上賀茂にある総合地球環境学研究所(地球研)の熊澤です。
平成28年10月から翌年2月にかけて針畑地域で実施した、古写真を使った3回のワークショップについてご報告します。
朽木で、ずっと残していきたい風景や行事や人のつながりなどについて、楽しみながら考える場を持ちたいと、古写真(昔の写真)を使ったワークショップ「朽木で、ずっと残していきたいものってなんだろう」を実施しました。この場が、過去の朽木について理解を深めながら、現在、そして未来について考えるきっかけとなること、また、古写真をとおして世代間のつながりづくりになることを目標として企画しました。
平成28年7月から9月に、市場集会所で実施した古写真を使ったワークショップは、朽木市場地区に近い地域の古写真を用いて、30代から70代の方々のべ46名が朽木に残していきたいものやことについて話をしました。
報告は下記のリンクからご覧ください。
「朽木でずっと残していきたいものってなんだろう 世代をつなぐ朽木の今昔写真」
第1回「昔の写真を見て語ろう
第2回「今の写真を撮って、昔の写真と比べてみよう」
第3回「私が未来に残したい風景やもの、ことの写真」
をご覧ください。
10月29日に実施しました、第1回「昔の写真を見ながら、お話しましょう」の報告で、ワークショップ3回の構成や準備について掲載していますのでご覧ください。
11月19日に実施しました、第2回「針畑地域でここが変わったなと思える風景や暮らしの写真を持ち寄り、お話しましょう」の報告もあわせてご覧ください。
さて、第3回は、「『残していきたいもの』を語らう」を目的に雪降る中、朽木西小学校官舎にて16名の方にご参加いただき実施しました。
今回も案内人は、地球研の気候適応史プロジェクトの研究員(現在は上級研究員)で歴史学が専門の 鎌谷かおるさんです。
地域に「残していきたいもの」とは何なのかを考えるために、前半、第1回と第2回で見ていただいた写真をふりかえり、今と昔の風景や人々の様子から「針畑は何でできているのか」を考えました。写真で切り取られたいろいろな「場面」とその変化から、針畑の方々がこれまで何とつながってきたのかに気づき、どのつながりを、どのように残していきたいのかを考えるためです。
写真は、「自然とのつながり」、「(針畑)地域内のつながり」、「(針畑地域と)他の地域とのつながり」、「人とのつながり」という視点から紹介しました。
写真で切り取られた場面を紹介しています。

後半は、「針畑の魅力をどうやって伝えるか」を考えました。
テーマを「未来の針畑で暮し、生きるかもしれない人たちに魅力を伝える」という設定でワークを行うことにしました。このような設定によって、参加者が「未来の針畑に残していきたいもの」を考えやすくなるのでは、と考えたからです。
また、誰に魅力を伝えるのか、伝える相手が具体的な方が考えやすくなりますので、「針畑に移住しようか迷っている若い夫婦に語りかける」と設定しました。夫婦が道の駅くつき新本陣から、不動産屋さんの用意した「バス」に乗り、各地区を訪ねて回ります。参加者は、自分が住んでいる地区にバスが着いたら、その夫婦に対して針畑の魅力を一言で伝える「殺し文句」を語りかける、ということにしました。
せっかくなので、少しでも臨場感を高めたいと、事前に道の駅から針畑地域をぐるりと回って大津市葛川梅ノ木町の国道367号線との交差点に至る道のりを動画で撮りました。まるで夫婦がバスから見ているように、道のりを映像で見ながら、各地区に着いたらその魅力を伝えていただきました。

参加者に示されたお題とルールは、以下に示す通りです。
【お題】
「30代の夫婦が針畑に移住しようか迷っています。
あなたなりの『殺し文句』を言ってください。
ただし、以下の言い回しでお願いします。」
☆ルール☆
以下の言い回しでお願いします。
「針畑は~やけど、~やでえ」
「30代の夫婦が針畑に移住しようか迷っています。
あなたなりの『殺し文句』を言ってください。
ただし、以下の言い回しでお願いします。」
☆ルール☆
以下の言い回しでお願いします。
「針畑は~やけど、~やでえ」
さて、どのような「殺し文句」が語られたのでしょうか。
針畑の自然に注目して言葉を紡いでくださったのは、小入谷、中牧、古屋の各地区にお住まいの方々でした。合作で「殺し文句」を考えてくれました。
「針畑はちょっと不便やけど、自然が多いし、水も空気も美味しいよー・・・ま、雪は降るし、積雪は多いし、バスはしょっちゅう止まるし、せやけど、せやけど雪景色がきれい」。
3名の方々から紡がれた言葉は、不便さ、ときには動物による被害といったものと引き替えに、得られる自然の多さと美しさは変え難いといったものでした。
そして、針畑に住む上での目的や目標に注目した言葉を紡いでくれたのは、別の3名の方々でした。
たとえば、小入谷に住まわれている方が投げかけたのは・・・
「・・・・周りの環境、周りにある生活に、ある程度合わせたら別に問題ないし。そんで、自分がどういう思いでここへ住もうかな、住んでみようかな、と思って来たかという気持ちが、一番問題だと思うんですよね。・・・自分で好んでここに住むと」
「いろんな生活のことも、食事のことも、あるいは、車ないと住めへんとか、いろんなん(いろんなこと)あると思うけど、それらも全部踏まえて、やっぱり自分もこういう田舎を求めて、・・・住みたいなと思う人だったら、若くても十分住めると思うんですね」
「人それぞれ、いろんな目的があると思うのね。別に一から十まで田舎の人に合わす必要ないやろうし、自由気ままに住める。逆に言うたら、住めるところがここなんだ、と思うんですね・・・」
3名の方々から紡がれた言葉は、目的や目標を持っていることが大事で、ここでの暮しを選んだことを思って生活していけば、そんなに大変なことではないといったものでした。
発表の様子です。

朽木地域の最も奥の地域で、みなさん「~やけど」のニュアンスをどこかに含みつつ、若い夫婦に針畑の魅力をアピールしてくださいました。
終了後のアンケートでは、「全体にポジティブな話が多くあった。」とのコメントが寄せられました。確かにそのような雰囲気の中で語られた、それぞれの「殺し文句」だったと思います。その一方、「針畑の未来について良いイメージを描けない(こと)に残念な気持ち」とのコメントも寄せられました。紡ぎ出された言葉たちは、どんなにポジティブなものであっても、未来について良いイメージが描けないことと背中合わせの状況から生まれたもの。これをどのように受け止めて前に進めばよいのか、本当に難しい課題です。
今後のワークショップへの要望には、「新しい家族(移住者)たちがここで暮すことが、できるように何が出来るかについて話す場がほしい。」「話すだけでなく、この地域をいろいろ見る機会を作った方が良い気がする。」「他市町での事例も参考にさせていただきたい。」といったものがありました。
さて、果たしてみなさんの「殺し文句」は夫婦の心に届いたのでしょうか。夫婦が移住を決めたとすれば、それにはきっと理由があるはず。そして、それが分かれば、私たちがこれからすべきことが見えてくるのではないでしょうか。次には、これを探ることができるような内容のワークショップを企画していきたいと思います。寄せていただいた要望には、次の企画を考える上で重要なヒントがたくさん含まれているように思います。ぜひ活かしていきたいですし、一緒に考えていければ幸いです。
ワークショップで行ったこと、見えてきたことについて、5月21日(日)に高島市森林公園くつきの森の「ユリノキ祭」でポスターにして展示しました。
針畑地区での取り組みをまとめたポスターはこちらから見ていただけます。
最後になりましたが、ワークショップに参加してくださったみなさん、写真を貸し出してくださったみなさん、ありがとうございました。そして、今年度も引き続きよろしくお願いいたします。
主要参考文献
[1] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 通史編』, 高島市, 294pp.,2010
[2] 朽木村史編さん委員会『朽木村史 資料編』, 高島市, 264pp.,2010
タグ :朽木のみんなと円卓会議
Posted by たかしま市民協働交流センター at
17:40
│たかしま・未来・円卓会議報告


